近年、テレビ番組やネットニュース、SNSなどでよく見かける「シェアリングエコノミー」。聞いたことや利用したことのある有名なサービスもその一部で、生活するのに欠かせないという方もいるでしょう。
シェアリングエコノミーは環境に優しいという側面もあり、これからますます加速していくことが予想されます。しかし、まだその言葉に馴染みのない方にとっては、どのようなもので、どのようなメリットがあるのかいまいちイメージしにくいですよね?
そこで今回は、シェアリングエコノミーの種類や、拡大した背景、メリットなどを解説したいと思います!
シェアリングエコノミーとは

シェアリングエコノミーとは、個人や企業などでモノ・スペース・スキル・時間といった「遊休資産(稼働されていない資産)」を売買・貸し借りを、インターネット上のプラットフォームを介してシェアをする新しい消費のスタイルです。シェア(共有)するビジネスなので、「共有経済」「シェアエコ」とも言われています。
2021年シェアリングエコノミー調査報告によると、平成20年度から比べて30年度の市場規模は12兆円の増加額でした。これは携帯電話サービス業界の12.5兆円に匹敵する規模で驚異的な成長性で、日本の市場全体で見ても主要な業界の1つと言えます。
一般社団法人シェアリングエコノミー協会によると、「シェアリングエコノミー」は主に5つに分類されます。
シェアリングエコノミー ①スキル(Skill)

シェアリングエコノミー協会に登録されているスキルは86サービスあり、以下のような業種が代表的です。
- 家事
- 介護
- 育児
- 知識(翻訳・プログラミング・デザイン・音楽/動画編集など)
- 教育(ピアノ教室紹介・子ども向けのお迎え付き語学教育など)
- スキルや得意なことを売り買いできるフリマサイト・音楽に特化したスキルをシェアするマーケット
2016年に日本に上陸し、10都市以上でフードデリバリーサービスをしているウーバーイーツ(Uber Eats)も登録されており、スキルシェアの認知度はますます上がってきていると言えます。
参照 一般社団法人シェアリングエコノミー協会 シェアサービス一覧 シェア領域:スキル
シェアリングエコノミー ②空間(Space)

シェアリングエコノミー協会に登録されている空間は52サービスあり、以下のようなタイプのものが代表的です。
- 住居などのルームシェア
- 駐車場
- 会議室
- コワーキングスペース
- レンタルオフィス
- シェアアトリエ
- トランクルーム
- バケーションレンタル(民泊)
- レストランシェア
民泊サービスのエアビーアンドビー(Airbnb)は日本で世界で初めてのアライアンス組織(*1)を設立し、自治体・企業と連携をする方向で進めています。
今は新型コロナウイルスの影響を受けていますが、一棟貸しの民泊は世界的に人気が高まっており、テレワーク・ワーケーション・ステイケーションなど、コロナ禍での働き方の変化により民泊の可能性が広がっています。
*1 アライアンス組織:企業同士が連携し、業務・生産・技術・資本などの提携を全てを包括している組織
参照 一般社団法人シェアリングエコノミー協会 シェアサービス一覧 シェア領域:空間
シェアリングエコノミー ③モノ(Goods)
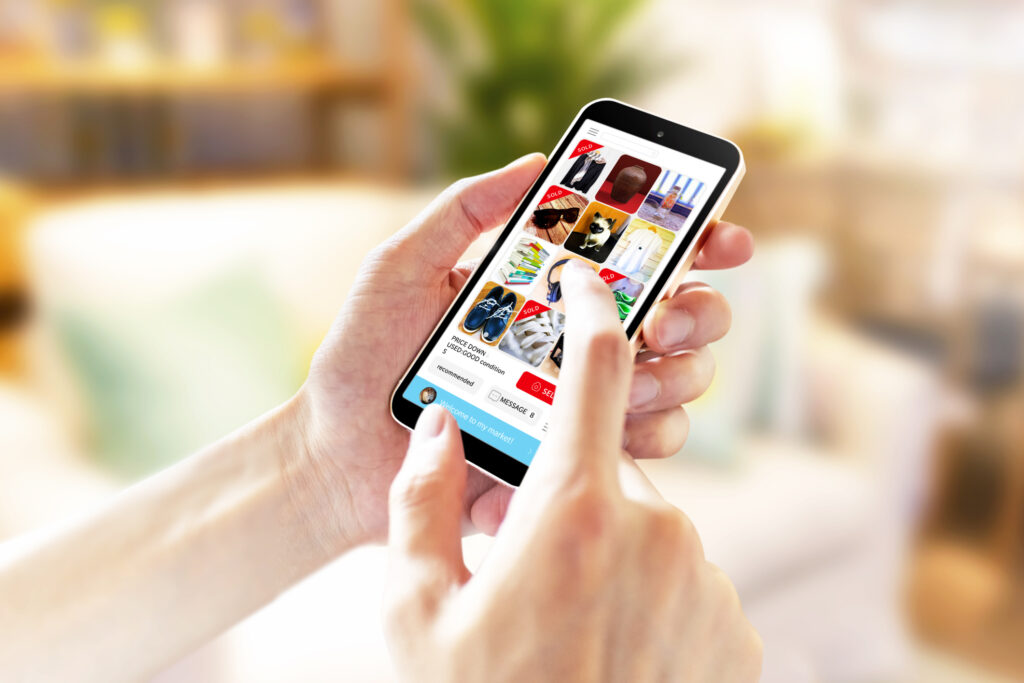
シェアリングエコノミー協会に登録されているモノは35サービスあり、以下のようなサービスが代表的です。
- モバオクやメルカリなどのフリマアプリやオンラインマーケット
- モノの貸し借りのアプリ
- 子供服のお下がりやウェディングドレスのシェア
- カメラや家電、ベビー用品などのレンタル
- ショップモビリティ(キッチンカーなど様々な業態の移動店舗が停まる場所をシェアする)
参照 一般社団法人シェアリン グエコノミー協会 シェアサービス一覧 シェア領域:モノ
シェアリングエコノミー ④移動(Mobility)

シェアリングエコノミー協会に登録されている移動は14サービスあり、以下のようなタイプが代表的です。
- カーシェアリング
- ライドシェアリング
- シェアサイクル
- 電動キックボードのシェア(小型特殊自動車として公道の走行が認められている)
なども登録されています。
2016年から京都府丹後市でNPO法人「気張る!ふるさと丹後町」が運行の主体となって地元住民がドライバーになり、ウーバーのアプリで即時に配車する事業「ささえ合い交通」を行っなっています。
同じく2016年に北海道中頓別町では「なかとんべつライドシェア事業実証実験(*2)」を行うなど、「移動シェア」のニーズは地域の高齢者の移動手段としてますます増えていくでしょう。
*2 なかとんべつライドシェア事業実証実験は、地域のバス利用者の減少に伴い、バスの維持にかかる負担・不便さを解消するため、地域住民がドライバーとなって配車する運行実験。実験が実証されて2019年からは「なかとんべつライドシェア」としてウーバーのアプリを利用し、有償で運行している。
参照 一般社団法人シェアリングエコノミー協会 シェアサービス一覧 シェア領域:移動
シェアリングエコノミー ④お金(Money)

シェアリングエコノミー協会に登録されているお金は4サービスあり、クラウドファンディングが代表的です。
クラウドファンディングは寄付型・購入型・金融型の3種類に大きく分けられ、商品やサービス、アイデア、支援などへの資金調達が一般的な目的です。自己資金が少なくても、資金を募って夢への挑戦ができるのが大きな魅力です。
イベント的に告知して認知度を広めるマーケティング手法としても有効であり、毎年多くの事業がクラウドファンディングを通して生まれています。クラウドファンディングの市場規模は年々大きくなっており、2014年から2018年の間で支援額の伸びはなんと約10倍。これからもますます大きなシェアリングエコノミーとして成長していくものと思われます。
参照 一般社団法人シェアリングエコノミー協会 シェアサービス一覧 シェア領域:お金
参照 TEAMクラファン – クラウドファンディングの市場規模とWithコロナでの今後の展望について
シェアリングエコノミーが広まった背景

シェアリングエコノミーで主に活用されているのがインターネットとスマホアプリ。多くの人たちがいつでもどこでも、インターネットを利用できるようになり、オンライン決済もスムーズにできるようになりました。
またSNSなどのソーシャルメディアが一般的に認知・利用されるようになったことで、オンライン上でのやりとりに対する抵抗を覚える人が減少。プラットフォームの使いやすい設計も手伝い、シェアリングエコノミーは一気に広まりました。
加えて、時代の流れや消費者の意識の変化も影響しています。日本で考えると高度成長期から人々の暮らしは豊かな生活になり、たくさんのモノに囲まれてきました。人々はモノを所有したい気持ちよりも価値がある体験やサービスを求めるようになってきています。そういった志向から「消費」の内容が変わり、必要なときだけ利用することができるシェアリングエコノミーが注目されたのです。
他にも、1990年から日本は景気の低迷・非正規雇用者の増加などの理由により若い世代の生活は厳しく、節約嗜好が強い傾向が見られます。新たにモノを買うよりシェアリングエコノミーを利用する方が経済的と考える人がいるのも、広まった背景と言えるでしょう。
シェアリングエコノミーのメリット・デメリット
シェアリングエコノミーにはどんなメリット・デメリットがあるのか、それぞれ見ていきましょう。
シェアリングエコノミーのメリット
環境に優しい

例えばメルカリのようなフリマアプリを使うことで、不用品の廃棄量を減らせます。またシェアカーを使うことで、1人1台が車を持つよりも温室効果ガスの排出量を抑えることができます。
近年はSDGsの認知度が広まりや、エコロジー・サスティナビリティに注目する人が増えていることもあり、今後はこのようなサービスがますます注目を集めそうです。
余ったモノや空間などを活用することでムダな消費を減らし、スキルや資源を有効活用する。そうすることで、よりサスティナブルな社会の実現に近づくのではないでしょうか。
参照 SDGsの多面性とシェアリングエコノミー ー2021年シェアリングエコノミー調査報告 第5回ー
幸福度の向上

シェアサービスは、興味・関心などの価値観が近い人と出会う接点にもなり得ます。
2021年シェアリングエコノミー調査報告によると、サービス利用者と非利用者では、利用者のほうが高い幸福度を感じているという結果も出ています。
このように、GDPに反映されづらいようなポジティブな側面があるのも、シェアリングエコノミーの特徴の1つだと言えます。
参照 シェアリングエコノミー躍進のエンジンは幸福度の増進-2021年シェアリングエコノミー調査報告 第3回-
所有する必要がなくなる

必要なモノやサービスを必要なときにシェアすることで、使いたいものを全て所有する必要がなくなります。また購入やメンテナンスのための出費も不要なので、コスパ面でもかなりお得に利用できるのもメリットです。
例えば、住まいはAddress、車はCarecoなどの月額制シェアサービスを使えば、提供地域であればどこでも身軽に生活することが可能。これまでの所有という概念に破壊的インパクトを与えるものと言えるでしょう。
参入障壁の低さ

シェアビジネスの提供側にとっても、すでに所持している遊休資産を利用して始められる場合は、初期費用をかなり抑えて事業を立ち上げることが可能です。
シェアできるモノを提供でき、それに需要があれば成り立ちやすい。そんな参入障壁の低さも、シェアリングエコノミーの広がりを加速させている理由の1つだと言えます。
シェアリングエコノミーのデメリット

今、シェアリングエコノミーは急速に普及しており、法の整備が追いついていないのが現状です。そのため、利用者・提供者ともに、様々な点に注意する必要があります。
シェアリングエコノミーの多くは個人間取引なので、商品・サービス・利用者に問題がある場合も、自分で見極める力や解決する行動が必要となります。例えば、他の類似商品と比べて安価すぎるものなどに関しては、偽物かどうかを念入りに確認するなど、トラブルにならないように選ぶ必要があります。
リスク回避の対策として、提供者・利用者の評価のチェックや、保険で補償できるものは保険の加入をするなどが挙げられます。しかし、多くのプラットフォーム会社でトラブルサポートが用意されてはいるものの、海外とのやりとりの場合、言語の問題でサポート窓口とスムーズに連絡が取れないというケースもあり得ます。
また、今は新型コロナウイルスの流行により、モノや空間などのシェアをするのはリスクがあると考えられ、接触を伴う対面型のサービスが敬遠される傾向が見られます。
一方、オンラインなどの非対面型サービス・スキルシェアサービス・フリマサイト・デリバリーサイトなど、大きく伸びているサービスも。どのようなサービスが生き残るかの予想は難しいものの、シェアリングエコノミーそのものはこれからの新しい社会に深く根付いていくでしょう。
最後に
どうしても所有したいものは購入して、シェアで十分なものは皆んなで使う。持てることがステータスだった時代から、分け・補い合う時代に変化しているのかもしれません。
WEELSではこれからも、所有に対する人々の考え方がどのように変わっていくのかに注目していきたいと思います。

インテリアスタイリングやファブリックの仕事を経て、結婚を機に都会から田舎暮らしへ。今は山暮らしをしながら3姉妹の子育て中。趣味はお菓子作り。


